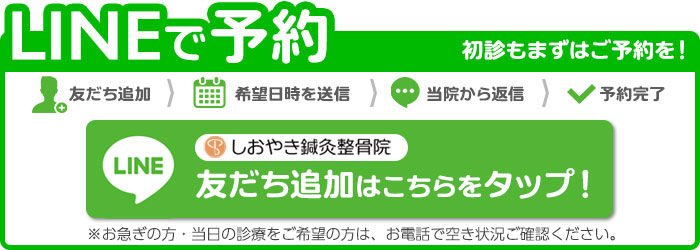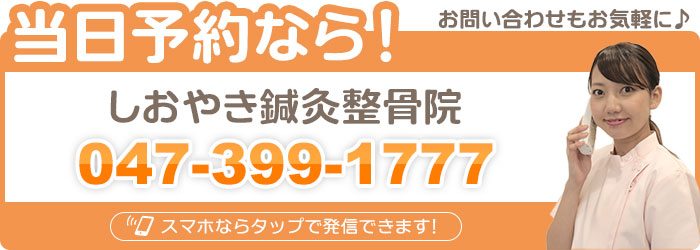はじめに
「生理が近づくと気分が落ち込む…」
「生理のときはお腹の痛みで仕事に集中できない…」
このように、生理痛やPMSに悩まされている女性は少なくありません。
特に20代〜30代は、仕事・プライベート・家事などで忙しく、症状が生活に大きく影響してしまうこともあります。
この記事では、
● 生理痛が起こる原因
● PMSの仕組みと原因
● ツボ押しでできるセルフケア
をやさしく解説します。
1. 生理痛が起こる原因
1-1.子宮の収縮による痛み
生理中、子宮は経血を押し出すために縮みます。
このとき「プロスタグランジン」という物質が多く出すぎると、子宮が必要以上に収縮して、強い痛みにつながります。
1-2. 血流の悪さと冷え
冷えや運動不足で血流が滞ると、子宮まわりの筋肉が硬くなり、痛みが増す傾向があります。
1-3. 自律神経の乱れ
ストレスや睡眠不足で自律神経が乱れると、ホルモンバランスも崩れ、生理痛が重くなることがあります。
2. PMS(生理前症候群)とは?

2-1. PMSの仕組み
PMSは「排卵から生理が始まるまで」の期間に起こる心や身体の不調のことです。
この時期には、女性ホルモンの エストロゲン(卵胞ホルモン) と プロゲステロン(黄体ホルモン) が大きく変動します。
● エストロゲン:心身を安定させるホルモン
● プロゲステロン:妊娠を維持するためのホルモン
このバランスが乱れると、脳内のセロトニン(幸せホルモン)が減り、気持ちが不安定になりやすくなります。
2-2. PMSの主な原因
● ホルモンバランスの変動
排卵後にプロゲステロンが増え、体温が上がり、むくみやだるさが出やすくなる。
● 自律神経の乱れ
ストレスや睡眠不足で自律神経が乱れると、頭痛・イライラ・不安感が強くなる。
● 栄養バランスの乱れ
甘いものやカフェインのとりすぎで血糖値が乱れ、気分の浮き沈みが大きくなる。
● 血行不良
体が冷えると血流が悪くなり、肩こり・頭痛・だるさにつながる。
2-3. PMSのよくある症状
- 心の症状:イライラ、不安、落ち込み、集中力の低下
- 体の症状:頭痛、胸の張り、むくみ、便秘、眠気、だるさ
これらは人によって出方が違い、「自分だけがつらい」と感じてしまうことも少なくありません。
3. 生理痛・PMSをやわらげる7つのツボ
ここからは、症状をやわらげるためにおすすめのツボを紹介します。
ツボ押しは 自宅で簡単にできるセルフケア なので、気づいたときに取り入れてみましょう。
3-1. 三陰交(さんいんこう)
● 場所:内くるぶしの上、指4本分。
● 効果:冷え・むくみに効果。

3-2. 気海(きかい)
● 場所:おへそから指2本分下。
● 効果:下腹部の冷えや生理痛を和らげる。

3-3. 関元(かんげん)
● 場所:おへそから指3〜4本分下。
● 効果: 婦人科系トラブルに広く効果的。
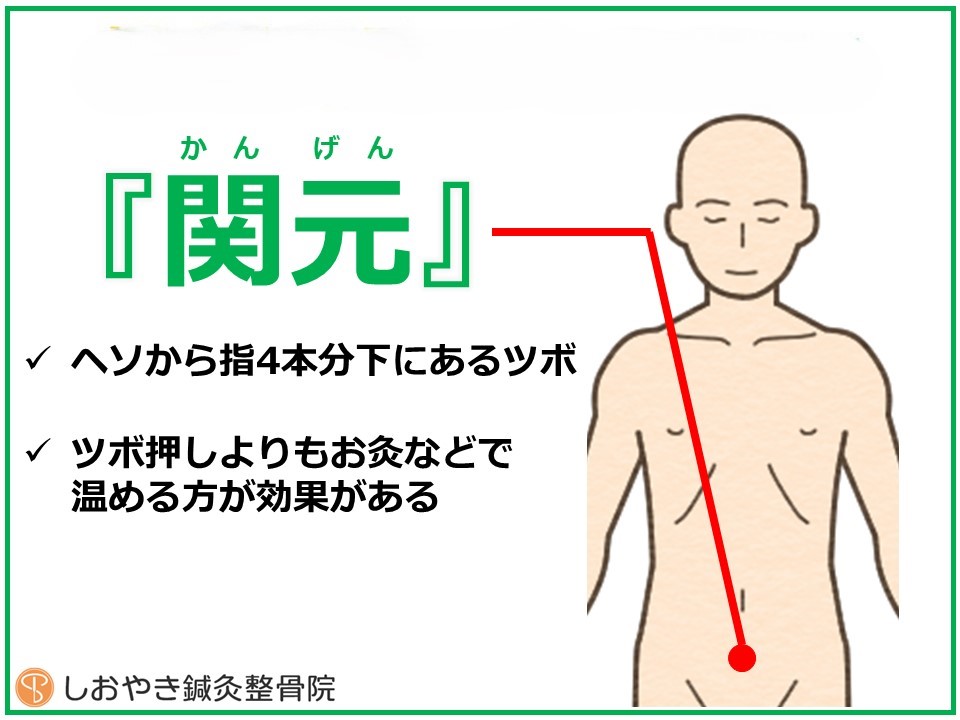
3-4. 血海(けっかい)
● 場所:ひざのお皿の内側から指3本分上。
● 効果:血流を促進し、生理不順や経血トラブルに。
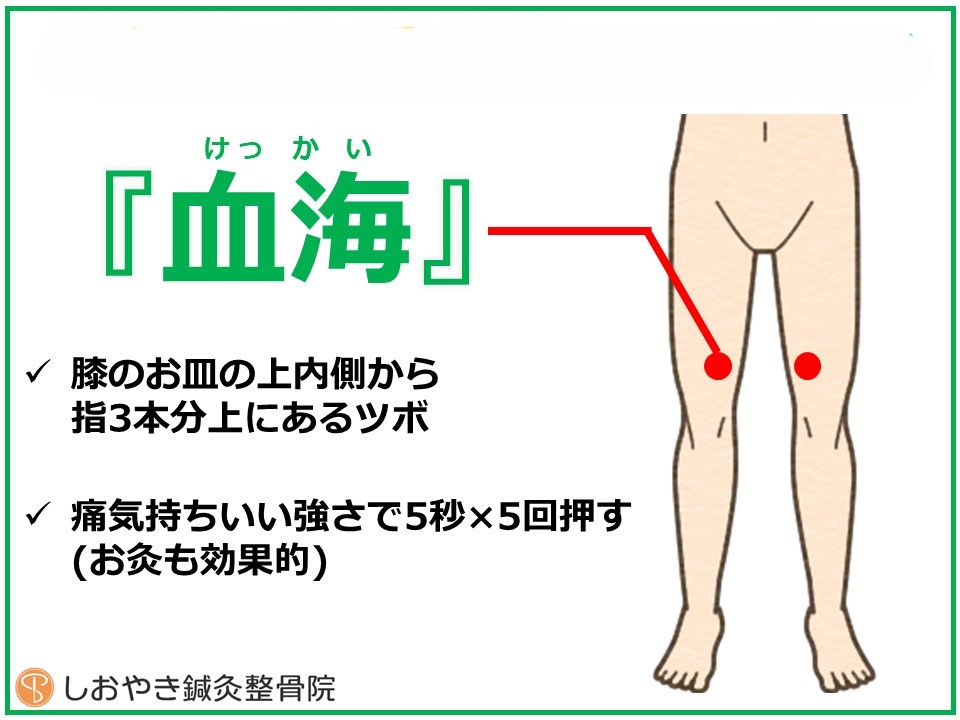
3-5. 合谷(ごうこく)
● 場所:手の甲の親指と人差し指の間。
● 効果:自律神経を整え、頭痛・イライラに。
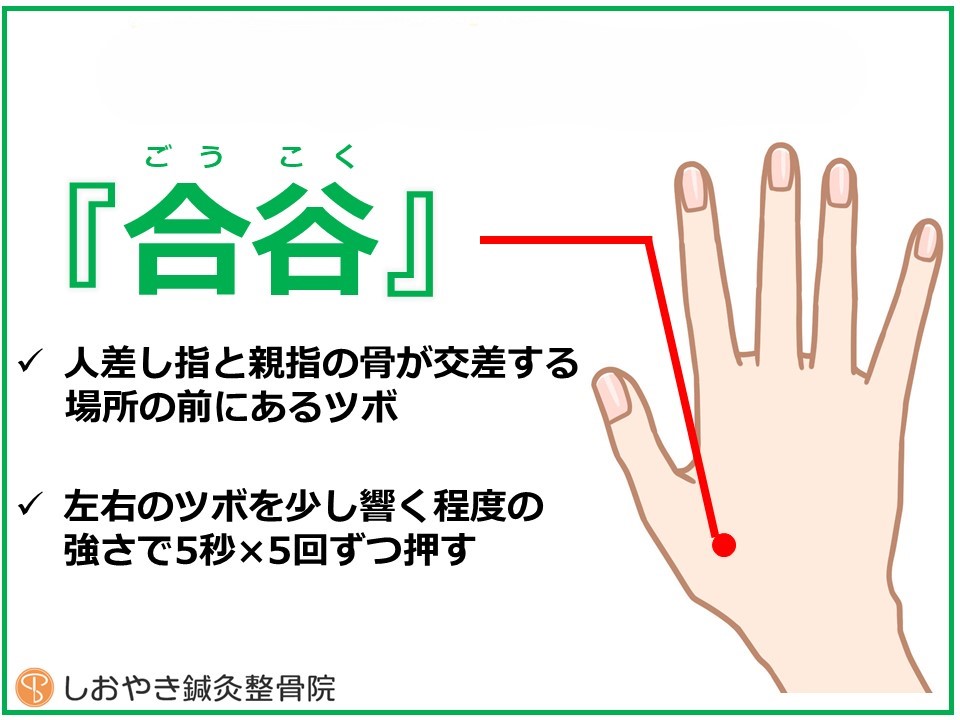
3-6. 太衝(たいしょう)
● 場所:足の甲の親指と人差し指の骨の間。
● 効果:ストレスや気分の高ぶりを落ち着ける。
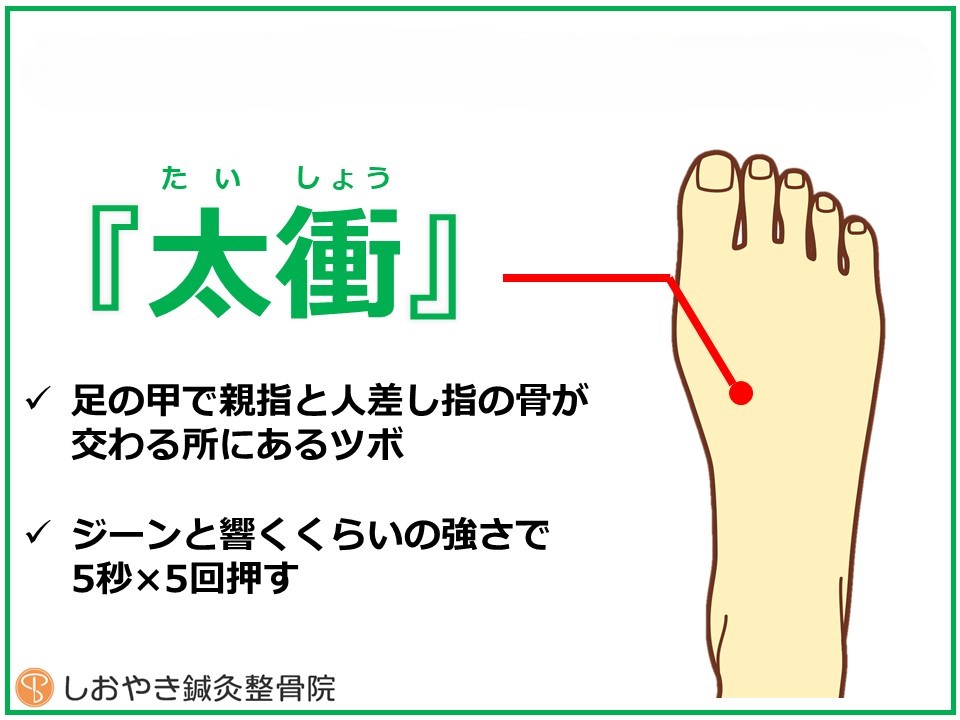
3-7. 天柱(てんちゅう)
● 場所:首の後ろ、髪の生え際で太い筋肉の外側。
● 効果:頭痛・肩こり・不眠に効果。

4. ツボ押しのコツ
- 親指でゆっくり 3〜5秒押す
- 強すぎず「気持ちいい」と感じる力加減
- 毎日少しずつ続けることで効果が出やすい
5. ツボと合わせたい生活習慣
- 身体を冷やさないように温かい飲み物を選ぶ
- 軽い運動やストレッチで血流をよくする
- 睡眠のリズムを整えることで自律神経を安定させる
まとめ
生理痛やPMSは「女性なら仕方ない」と思われがちですが、原因を理解し、ツボ押しや生活習慣を取り入れることで、症状をやわらげることができます。
特に今回紹介した 三陰交・気海・関元・血海・合谷・太衝・天柱 の7つのツボは、毎日のセルフケアとして取り入れやすい方法です。
無理なく続けていくことで、心と体のバランスが整いやすくなります。